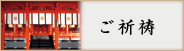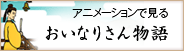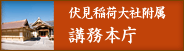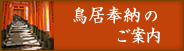- トップページ
- しるしの杉
しるしの杉
平安時代も中期以降になると、紀州の熊野詣が盛んとなり、その往き帰りには、必ず稲荷社に参詣するのが習わしとなっていて、その際には、稲荷社の杉の小枝=“しるしの杉”をいただいて、身体のどこかにつけることが一般化していました。
『為房卿記』という文献には、永保元年(1081)10月、藤原為房が熊野詣の帰途、稲荷社に参詣し、杉枝を伐って笠に差し、京に入ったことが記録されています。
また、平家の勢いが頂上にさしかかろうとする平治元年(1159)12月10日、平清盛が熊野参詣の途中、京からの早馬が追いつき、前日に三条殿へ夜討があり御所が焼亡した、これはおそらくは平家を討とうとするたくらみに相違ない、という知らせが届いたので、清盛は急ぎ京へと引き返します。このような火急の際でもやはり「先づ稲荷の社にまいり、各々杉の枝を折って、鎧の袖にさして六波羅へぞつきにける」と、「保元の乱」に続く「平治の乱」の幕開けの模様が『平治物語』(古活字本)に記されています。
きさらぎやけふ初午のしるしとて稲荷の杉はもとつ葉もなし
新撰六帖 光俊朝臣
「初午に参詣した人々が、そのしるしとして、各々が杉の小枝をとっていくものだから、この日の稲荷山の杉はすっかり葉がなくなってしまった」と少々大げさな歌ですが、“初午”と“しるしの杉”が切りはなせない関係にあったことを如実に示して余りある和歌が残されています。この他にも、平安時代の新しい和歌の世界を築き上げた人々によって、“初午”や“しるしの杉”が多く詠われています。しかし“しるしの杉”は必ずしも、“初午”とだけ結びついたものではないことが、前出の藤原為房あるいは平清盛の稲荷詣に関する記述からおわかりいただけるでしょう。それほどに稲荷の“杉”は広く信仰される対象になっていたのです。そしてこの“杉”は、時として稲荷大神あるいは稲荷社を象徴しているもののように受けとめられていました。
太政大臣実頼公(天禄元年(970)没)の稲荷大神に対する信仰にその一端を見ることができます。
実頼公は日頃から端正な方でした。居館の南面した座敷からは、稲荷山の杉がはっきりと望めるので、その部屋へ冠をとったままお入りになることはめったにありませんでした。それと言うのも、当時は人前で冠をとることは最も無礼なこととされており、寝所でも冠をとらなかったほどで、ましてや神前では許されるはずもありませんでした。それで、時としてついうっかりと無冠のままこの部屋へ入られたような場合は、それをお気づきになるや袖で頭を覆って、ひどくうろたえ騒がれた、ということを『大鏡』では伝えています。
もう一つは文章博士の大江匡衡(長和元年(1012)没)の逸話です。ある時、匡衡が稲荷社の禰宜の娘に恋をしたため、正妻の赤染衛門のところへ長い間通わなくなってしまいました。そんな折、彼が禰宜の家にいる時に、
わがやどの松はしるしもなかりけり
すぎむらならばたずねきなまし
と随分皮肉った和歌を赤染衛門が遣わしました。これを見た匡衡はその後、禰宜の家へは足を踏み入れなくなり、元のさやに収まったと『今昔物語』(二十四)には書かれています。
熊野詣
平安期に入ると、熊野三山に参詣するいわゆる熊野詣がにわかに流行し、「蟻の熊野詣」といわれ、貴族たちが、熊野路に向かうようになりました。それに伴い当社はまた新しい信仰を賦与されることになりました。
交通事情の悪い当時、京都から熊野まで旅するのは、大変な危険が伴います。下手をすると途中で野垂死するおそれもありました。いかに信仰のための旅とはいえ、途中で生命を落としてはなんにもならない、そこで、熊野詣の人々は道中の安全を神々に祈願するのですが、その時一番頼りにされたのが当社であり、やがて稲荷大神が護法童子を遣わして道中の安全を守護してくれるという信仰が定着したのです。
そのため、熊野詣から帰洛した人々は護法童子をお返しするために、まっさきに必ず当社へ奉幣・お参りするようになりました。これを護法送りといい、院や上皇の帰洛の際はことに盛大だったようです。
※このコラムは『たくましい民衆のエネルギーに支えられた1200年の歴史』百瀬明治 京都新聞社刊「総本宮伏見稲荷大社」を参考にしました。