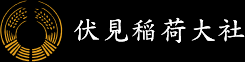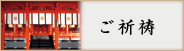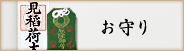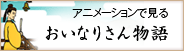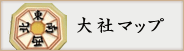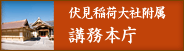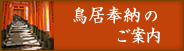当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」31号
| 変貌する稲荷山の神 | 水谷 類 |
| 風土記にみられる餅と天女と白鳥と | 瀧音 能之 |
| 稲荷明神と霊狐信仰 | 松前 健 |
| 民間信仰としての稲荷神 | 大藤 時彦 |
| 神社合祀と南方熊楠 | 黒岩 龍彦 |
| 平安時代の稲荷祭と祇園御霊会 | 岡田 莊司 |
| 苗見竹の風習 福島県の例二、三について | 岩崎 敏夫 |
| 中世狐相の一因子 | 石上 堅 |
| 石器時代における施朱の風習の出現と終焉の系譜 | 市毛 勲 |
| 稲荷と修験山伏 | 菊地 武 |
| 落語と稲荷 | 権藤 芳一 |
| 献句(山口誓子先生句碑除幕記念) | 『天狼』会員 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 角田 寛 坪原 喜三郎 |
| 稲荷大社附近 短歌 | 田中 順二 |
| 梁塵秘抄の稲荷十首 ―平安都市風俗の稲荷詣における男女の合歓性― |
渡邉 昭五 |
| 稲荷とダ枳尼天 | 高橋 渉 |
| 鎌倉の稲荷(上) | 三橋 健 |
| 農村における稲荷講の展開 ―尼崎市西昆陽の事例を中心に― | 森 隆男 |
| 一瓶塚稲荷縁起その他 | 西垣 晴次 |
| むささびの歌 | 三宅 清 |
| 続々・太郎稲荷繁昌志 | 宮尾 與男 |
| 稲荷信仰点描 | 鈴鹿 千代乃 |
| 稲荷講 | 平井 直房 |
| 神杉と鎮魂のまつり 三輪と稲荷 | 山上 伊豆母 |
| 銀座の稲荷 | 西尾 忠久 |
| 東海道本線「稲荷」駅 | 木村 博 |
| お稲荷さん・狐・文楽 | 角田 豊正 |
| 韓神の藝態傅承論 ―園韓神祭における 神宝舞からのアプローチ― |
小林 茂美 |
| 房総半島における稲荷信仰の展開 | 荒木 恵美 |
| 隅田稲荷神社物語 | いのうえ 田堂 |
刊行物「朱」30号
| 稲荷神のダブル・イメージ | 山折 哲雄 |
| 宇迦之御魂神の原義 | 友田 吉之助 |
| 古典文学と稲荷詣 | 春田 宣 |
| 天馳使と海人駈使 ―記紀における鳥神の意味― | 山上 伊豆母 |
| 稲荷前後 ―民族信仰の基底をめぐって― | 阿部 正路 |
| 伏見稲荷早春 | 国分 綾子 |
| お稲荷さんの祠 | 桑田 忠親 |
| 直江廣治編『稲荷信仰』を読む | 柴田 實 |
| 民俗語り狐神 | 石上 堅 |
| 守護と祟りのイナリガミ | 波平 恵美子 |
| 「小鍛冶」能楽寫生 | 近藤 喜博 |
| 陸前地方の狐塚について | 三崎 一夫 |
| 正月行事と司祭者 | 佐々木 勝 |
| 神社と茶道 | 永島 福太郎 |
| 伏見稲荷大社と空海 | 百瀬 明治 |
| 阿刀弘文翁と針小路文庫の稀覯典籍 ―特に稲荷大社の文献について― |
小島 鉦作 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 小島 鉦作 坪原 喜三郎 |
| 晩春の神域 俳句 | 桂 樟蹊子 |
| 思い出のあれこれ | 水野 深草 |
| 稲荷信仰と弘法伝説 | 渡邉 昭五 |
| 寛治八年の「稲荷霊会」 | 高橋 渉 |
| 続 太郎稲荷繁昌志 | 宮尾 與男 |
| 伏見のお稲荷さん | 芝田 米三 |
| 城下町・若松の屋敷稲荷について | 野沢 謙治 |
| 稲荷信仰と鉄 | 窪田 蔵郎 |
| 疱瘡稲荷 ―伊豆における疱瘡神の一資料― | 木村 博 |
| 伏見人形の“わらい” | 奥村 寛純 |
| 松江城山稲荷の式年神幸祭 | 島田 成矩 |
| 円空のお稲荷さま | 林 真作 |
| 『皆中稲荷神社』東京新宿 | いのうえ 田堂 |
刊行物「朱」29号
| 稲荷神鎮祭譚補遺 | 倉林 正次 |
| 白い鳥 葦原の瑞穂の国 | 桜井 満 |
| 春に詣でて 俳句 | 桂 樟蹊子 |
| 若葉の神苑 ―伏見稲荷大社にて― 短歌 | 中野 照子 |
| 刀工宮本能登守包則 ―稲荷山剣石打に就いて― | 草信 博 |
| イナリと鍛冶儀礼 | 阿基 米得 |
| 神馬 奉納者の心 | 荻野 三七彦 |
| 尾形乾山筆の伏見人形図について | 木村 博 |
| 江戸稲荷抄録 | 加藤 郁乎 |
| 稲荷神話の成立と天台・真言密教 ―説話の成立とその展開をめぐって― |
三谷 栄一 |
| スザノヲノミコトの遍歴 ―ハタ氏はどこから来たのか― |
吉野 裕 |
| 狐神転生譚の展開 | 石上 堅 |
| 稲荷信仰の発展と伝播 ―奈良県下における稲荷社の分布と民俗行事の分析から― |
森 隆男 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 羽倉 信也 坪原 喜三郎 |
| 春満の文学観抄 | 羽倉 信夫 |
| 大山為起 | 西田 長男 |
| おいなりさんと私 | 福本 武久 |
| 稲荷社と芝居 | 角田 豊正 |
| 津軽「高山稲荷」の信仰形態 | 高橋 渉 |
| お稲荷さんのお山巡り | 神馬 彌三郎 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。