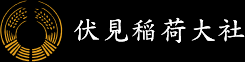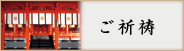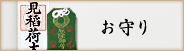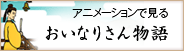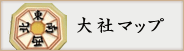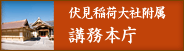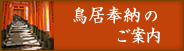当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」40号
| 伊奈利社と秦氏の活躍 | 上田 正昭 |
| 古代豪族秦氏の足跡 | 山尾 幸久 |
| 稲荷社と山崎闇斎 | 近藤 啓吾 |
| 稲荷大社史点描 | 永島 福太郎 |
| 稲荷と唱導資料 表白二題 | 小峯 和明 |
| 法華守護三十番神と稲荷大明神(上) | 三橋 健 |
| 『荷田講式』にみる中世神祇の諸相 | 岡田 莊司 |
| 稲荷神社の歴史と文学 | 田中 裕 |
| 美女になった狐 | 山口 仲美 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 川本 八郎 坪原 喜三郎 |
| 稲荷をめぐる絵画資料覚書 ―いわゆる世俗画について― |
岩田 由美子 |
| 稲荷祭に関する新史料二通 | 上島 有 |
| 献句 ―稲荷抜穂祭吟行― | 大円句会 |
| 秦公伊侶具とその子孫 | 瀧音 能之 |
| 明神、御覧ずらむに | 西木 忠一 |
| 伏見稲荷大社祭神考 | 吉野 裕子 |
| 伏見稲荷大社の異名「藤森稲荷」と「藤森」をめぐって | 榎本 直樹 |
| 地方都市における稲荷信仰 ―金沢の近代企業が祀る稲荷社の実態― |
小倉 学 |
刊行物「朱」39号
| 稲荷社と修験道 | 村山 修一 |
| 稲荷社とその周辺の考古学的知見 | 久世 康博 |
| 方相氏小考 | 森田 悌 |
| 平安貴族と稲荷祭 | 中村 修也 |
| 平安時代の稲荷詣と女性 | 服藤 早苗 |
| 王朝女流私家集と稲荷 | 西木 忠一 |
| 稲荷明神と北野天神 ―「渓嵐拾遺集」にみる説話の変容― |
松本 公一 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 佐治 八重子 坪原 喜三郎 |
| 『大嘗会儀式具釈』管見 | 加茂 正典 |
| 狐に関する百科事典『霊獣雑記』 | 竹居 明男 |
| 稲荷信仰の懸仏 ―千葉県高照院の遺品をめぐって― | 山下 立 |
| 稲荷社殿に設けられた穴 ―弘法大師との関係を主点として― |
日野西 眞定 |
| 稲荷伝説考 ―附資料「女化稲荷縁起」― | 志村 有弘 |
| 志摩国鳥羽の子供の稲荷祭 | 岩田 貞雄 |
| 秦氏由来の遺跡踏査記(二) | 段 熙麟 |
刊行物「朱」38号
| 稲荷旅所神主について | 五島 邦治 |
| 初期の稲荷祭 | 五味 文彦 |
| 京都七条町に生きた人々 | 野口 実 |
| 道元と稲荷神 | 木村 清孝 |
| 寺のなかの稲荷神 ―浄土宗の場合― | 伊藤 唯真 |
| 西洋人のみた稲荷信仰 | 松村 一男 |
| 「稲荷縁起絵巻」私注 ―中世稲荷社をめぐる蘇生譚覚書― |
竹居 明男 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 芝田 米三 坪原 喜三郎 |
| 近世大坂地域の稲荷信仰 | 中山 すがね |
| 「更級日記」と稲荷 | 西木 忠一 |
| 加賀・能登における稲荷信仰と宇賀祭り | 小倉 学 |
| 「正一位」の神階と稲荷勧請 | 榎本 直樹 |
| 秦氏由来の遺跡踏査記 | 段 熙麟 |
| キツネの大好物はネズミのてんぷら | 安田 喜憲 |
| 稲荷社における三家・両家について ―対立と緩和・共生への足跡― |
朱編集部 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。