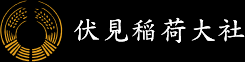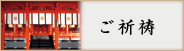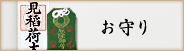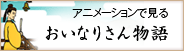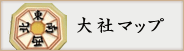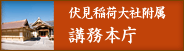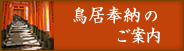当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」55号
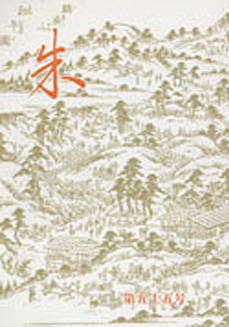
| 宇喜多秀家夫人の「御病」と伏見稲荷社 -「狐狩」と「陰陽師狩」をめぐってー |
河内 将芳 |
| 羽倉風のゆくえ | 一戸 渉 |
| 野狐庵魯文と稲荷 | 丹羽みさと |
| <穴>の境界論 -山本作兵衛の炭坑画に見る狐ー |
今井 秀和 |
| <狐>の喩と源氏物語 | 櫻井 清華 |
| 卜部本神名帳頭註 「伊奈利社」 再論 | 高藤 昇 |
| 渋谷の稲荷 | 石井 研士 |
| 狐塚遺跡、狐塚古墳の起源 | 片岡 宏二 |
| 都市開発と稲荷神社 -東京都品川区の敷地利用の分析からー |
渡部 鮎美 |
| 「くれなゐの末摘花」の心 -蓬生の女君の形象についてー |
西 耕生 |
| 正一位豊成稲荷と木津亀之助 -根津清太郎および谷崎潤一郎と関連させつつー |
千葉 俊二 |
| 「於岩稲荷験玉櫛」と五代目尾上菊五郎 ―「四谷怪談」大詰の演出をめぐって― |
日置 貴之 |
| 伏見宮家の南御方 ―その物詣を中心に― |
松薗 斉 |
| クイズ狐の鳴き声 | 山口 仲美 |
| 高岡瑞龍寺と稲荷大明神 -前田利長菩提寺に祀られる意義ー |
高尾 哲史 |
| 高山昇と皇典講究所 | 齊藤 智朗 |
| <資料紹介>霊元院仙洞稲荷社月次御法楽和歌 | 八木意知男 |
| 伏見の刊行図と版元 | 三好 唯義 |
| 百済弥勒寺の舎利奉安記について | 稲田奈津子 |
| 日本文化の心「いかす」 | 鈴木 榮子 |
刊行物「朱」54号
| 神楽歌の音振について | 遠藤 徹 |
| 『今昔物語集』巻二十八第一話 「近衛舎人共稲荷詣重方値女語」試論 -巻二十八の主題と巻頭話としての意味- |
渡辺 麻里子 |
| 朝比奈の釣狐 | 金子 健 |
| 玉藻譚と南北歌舞伎 -「三国妖婦伝」-と「玉藻前御園公服」 |
高橋 則子 |
| 平安貴族と「稲荷」を結ぶもの -和歌を手がかりとして- |
當麻 良子 |
| 中国の狐の話四題 | 坂出 祥伸 |
| 江戸文学と江戸の人口 | 棚橋 正博 |
| 近世日光の稲荷 | 山澤 学 |
| 浮世草子の狐 | 近藤 瑞木 |
| 曲亭馬琴『敵討二人長兵衛』考 | 佐藤 至子 |
| 白居易詩のなかの狐 | 後藤 昭雄 |
| 「上の字様」と「能勢の黒札」 -旗本・御家人の副収入- |
滝口 正哉 |
| 幕末滞日欧米人と王子稲荷 | 山下 琢巳 |
| 武蔵府中の稲荷の現在 -伝承の大國魂神社四方固め稲荷を通して- |
佐藤 智敬 |
| 狐疑城について | 山口 敦史 |
| 荷田(羽倉)信美ことども | 中澤 伸弘 |
| 「流造り」について | 太田 美喜 |
| 稲荷祭「天狗榊」天狗面の修理について | 安井 雅恵 |
| 経営者心理からみた稲荷信仰 -八王子織物業の歴史から- |
柏木 亨介 |
| 史料紹介 冷泉家時雨亭文庫本 『稲荷祇園行幸次第』 |
藤本 孝一 |
刊行物「朱」53号
| 辰刻の夢 -稲荷社に祈りを捧げた藤原頼長- |
谷口 美樹 |
| 荷田蒼生子と家集『杉のしづ枝』 -『杉のしづ枝』の書誌調査と考察- |
宮腰 寿子 |
| 『今昔物語』の狐 | 千本 英史 |
| 富くじと稲荷-江戸興行文化の一側面- | 滝口 正哉 |
| 落語「紋三郎稲荷」考 | 延広 真治 |
| 摂関二条良公の伏見稲荷信仰 | 山口 剛史 |
| 北の稲荷信仰 | 丸山 隆司 |
| 近世中後期関東における稲荷社の管理・運営~鷹場・開発の影響をめぐって~ | 菅野 洋介 |
| 九州脊梁山地の神楽と稲荷信仰 | 高見 乾司 |
| 「仁徳記」丸邇臣口子の機能 -「服下著二紅紐一青摺衣上」 「青皆変二紅色一」の解釈を中心に- |
田中 智樹 |
| 「神輿に立つ矢」に関するノート 大永八年の稲荷・東福寺喧嘩をめぐって |
河内 将芳 |
| 都の治助 -『けいせい鎌倉山』をめぐって- |
安冨 順 |
| 「名所図会」に描かれた稲荷社 | 西野 由紀 |
| 難読地名「一口(いもあらい)」と疱瘡稲荷 | 糸井 通浩 |
| 「保名」考-「玉藻の前」と、恨み「葛の葉」、二疋の狐が出会うとき- | 深澤 徹 |
| 高岡繁久寺と稲荷大明神 -前田利長廟所鎮守の可能性と諸要素- |
高尾 哲史 |
| 稲荷社近傍掃苔録 | 松本 丘 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。