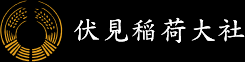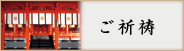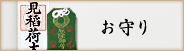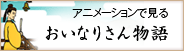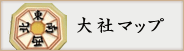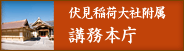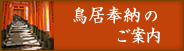当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」58号
| 稲荷上下旅所と二階旅所 -稲荷旅所の歴史のひとこまー | 五島 邦治 |
| 荷田派の延喜式祝詞研究 -稲荷祀官 大西親盛を起点にしてー | 松本 久史 |
| 小正月の狐狩り行事 |
赤田 光男 |
| 天に仰ぎ地に平伏して生きる -愛知県神道伏見稲荷東洋大教会の歴史ー | 磯前 順一 |
| 泗川の戦いにおける奇瑞演出の背景 -島津氏を護る狐と近衛家、幸若舞曲ー | 鈴木 彰 |
| 新釈「宗旦狐」 -黒に秘された秀吉と利休の相克ー |
冨田 弘子 |
| 「金春稲荷」 | 勝又 美代子 |
| 近代における神社講社制度の沿革と稲荷講 |
藤本 頼生 |
| 稲と田植と稲荷の力 -『於岩稲荷来由書上』を手がかりにー | 島田 潔 |
| 「琉球朱」の盛衰 -南島地域のおける朱肉・朱墨の生産を中心としてー |
渡辺 滋 |
| 鏡花と狐 | 梅山 聡 |
| ポップカルチャーにみる日本人と神 -稲荷信仰を手がかりにー | 平藤 喜久子 |
| 歌語「しるしの杉」考 | 鈴木 徳男 |
| 源九郎狐と大和郡山藩の稲荷 | 後藤 博子 |
| 天明狂歌師の「稲荷三十三社巡拝御詠歌」 | 小林 ふみ子 |
| 江戸における稲荷信仰の展開 -三囲稲荷の縁起と狐信仰をめぐってー | 谷口 貢 |
|
稲荷祭と寺内町本屋 |
万波 寿子 |
|
|
刊行物「朱」57号
| 大山為起『味酒講記』の成立過程とその注釈法 | 渡邉 卓 |
| ダキニ天の彫像と護法天部 | 伊東 史朗 |
| 江戸俳諧と「初午」 -元禄から宝暦にかけての史的展開- | 稲葉 有祐 |
| 茨田重方攷 -稲荷山での説話とその実像- | 北山 円正 |
| 近世後期における神祇伯白川家の「譜代」神社管掌 | 藤井 祐介 |
| 陽春寺三光稲荷の伝承について -金沢龍国寺高徳稲荷信仰の摂州伝播 |
高尾 哲史 |
| 戦国時代の稲荷の氏子圏について -予察- | 鋤柄 俊夫 |
| 「延久4年狐射殺事件」考 |
浜畑 圭吾 |
| 「元祖女みこし」の街の稲荷 -神田・須田町中部町会の変容と豊潤稲荷- | 秋野 淳一 |
| 〈資料紹介〉『秀雅百人一首』 |
八木 意知男 |
| ダキニ法の成立と展開 | 西岡 芳文 |
| 源氏物語の和歌と稲荷信仰 -歌垣・神事から夕顔・玉蔓へ- | 清水 婦久子 |
| 十一月八日の「御神楽」について | 米山 敬子 |
| 能〈小鍛冶〉における稲荷明神の姿 | 澤野 加奈 |
| 『八犬伝』の政木狐と馬琴の稲荷信仰 | 大屋 多詠子 |
| 足利氏と大倉稲荷 | 小川 剛生 |
|
稲荷社と藤原氏 |
木本 久子 |
|
荒廃した邸宅と狐 -『源氏物語』蓬生巻と白居易「凶宅」詩- |
長瀬 由美 |
刊行物「朱」56号
| 稲荷旅所の巫女「惣の一」 | 五島 邦治 |
| 源氏物語夕顔の巻と妖狐譚 -賀陽良藤の話をめぐってー | 新間 一美 |
| 民譚伝奇劇『袖簿播州廻』 -オサカベをめぐって | 安冨 順 |
| 稲荷山の信仰と伝承 ―和泉式部・ダキニテン― | 濱中 修 |
| 異色の『義経千本桜』 -天保十二年五月・中村座『裏表千本桜』をめぐってー | 光延 真哉 |
| 足尾銅山と稲荷神社 -鉱山地域と共に生きる稲荷ー | 冬月 律 |
| 万葉集における狐と薬狩 | 毛利 美穂 |
| 明治期の稲荷の広告 -引札と包裹(ほうか)にみるー | 中谷 哲二 |
| 過去から未来に手渡す「かたち」 | 下中 菜穂 |
| 刀八毘沙門天像の成立と発展 -伏見稲荷大社の刀八毘沙門天曼荼羅図を中心に- | 山下 立 |
| 近代期におけるイナリサゲの実態 | 大道 晴香 |
| 「城狐と刑部姫」 | 堀 誠 |
| 〈資料紹介〉 『国学四大人贈位祝祭歌集(仮題)』 | 八木 意知男 |
| 永井荷風の「狐」 | 多田 蔵人 |
| 栄稲荷神社 ―「地域」を記憶する社 | 萩谷 良太 |
| もう一つの平家物語 -稲荷町・末廣稲荷神社と先帝祭を中心にー | 森 誠子 |
| 勅撰集の稲荷の和歌 | 細川 知佐子 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。