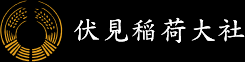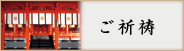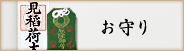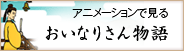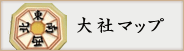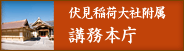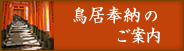当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」34号
| 玉と鍵のシンボリズム(下) ―黄表紙「扨化狐通人」の絵を読むこころみ― |
服部 幸雄 |
| 稲荷と狐と茶吉尼天 | 笹間 良彦 |
| 狐の化け方をめぐって | 小松 和彦 |
| 朱の思想 | 段 熙麟 |
| 花山稲荷と但馬国の農民 ―公卿花山院家参詣について― |
菊地 武 |
| 病気平癒祈願と稲荷信仰 ―特に疱瘡・瘡などの平癒祈願を中心として― |
大森 恵子 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 杉浦 翠 坪原 喜三郎 |
| 京に住みて 俳句 | 中山 詩鳥 |
| イナリ信仰管見 | 大野 芳則 |
| 風俗画報の稲荷 | 宮尾 與男 |
| 延享三年稲荷祠官江戸東下日記附解説 | 羽倉 敬尚 |
| 江戸のお稲荷さんにお参りして | 藤田 豊 |
刊行物「朱」33号
| 玉と鍵のシンボリズム(上) ―黄表紙「扨化狐通人」の絵を読むこころみ― |
服部 幸雄 |
| 山岳信仰の概念 | 高橋 渉 |
| 狐とお稲荷さん(その二) | 渡邉 昭五 |
| 土地の占有観念と稲荷信仰 | 波平 恵美子 |
| 鎌倉の稲荷(下) | 三橋 健 |
| 陽春狐媚笑譚 ―素朴な稲荷神にまつわる神話・伝説の学問的考証と江戸風俗川柳を交えながらの風俗夜話― |
石上 堅 |
| 静日抄 俳句 | 中山 詩鳥 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 白井 永二 坪原 喜三郎 |
| お稲荷様に参詣して 短歌 | 平井 乙麿 |
| 山城国稲荷山の経塚について | 佐野 大和 |
| 山城稲荷山経塚発掘遺物の研究 | 岩井 武俊 |
| 山城稲荷山経塚及発掘遺物に就きて | 高橋 健自 |
| 往時、関八州の狐たちで賑わった 王子稲荷神社 | いのうえ 田堂 |
| 福大神のことども | 石上 堅 |
| 銀座のお稲荷さんめぐり | 西尾 忠久 |
| 大都市とその近郊の稲荷祠(續) ―東京の西・川崎の北部― |
藤田 豊 |
| 漢字「朱」の解釈 | 田中 重久 |
刊行物「朱」32号
| 産鉄の豪族・秦氏と稲荷神 | 沢 史生 |
| 狐とお稲荷さん(その一) | 渡邉 昭五 |
| キツネ憑き仮考 | 中村 禎里 |
| 狐の境界性 | 飯島 吉晴 |
| 眷属列伝の意図 ―叙説「日本の狐物語」― | 野村 純一 |
| 海と稲荷信仰 | 菊地 武 |
| 江戸の稲荷めぐり | 興津 要 |
| 雑華抄 俳句 | 中山 詩鳥 |
| 「好去好来」宮司対談 | 佐々木 周二 坪原 喜三郎 |
| 稲荷山夕唱 短歌 | 福本 夕紀 |
| 大山為起関係文書を拝見して ―「神拝伝初重」の感懐― |
近藤 啓吾 |
| 松山における大山為起 | 白方 勝 |
| 稲荷社旧祠官波多忌寸為起撰「天照坐伊勢二所皇太神宮御鎮座次第記葦水草」に就きて | 菟田 俊彦 |
| 神道家大山葦水為起のことども | 羽倉 信一郎 |
| 大山為起翁小傅 | 羽倉 信一郎 |
| 隠れたる神道家大山為起翁の傅 | 山本 信哉 |
| 雨の稲荷山 ―柳田折口両大人の伏見参篭― | 菟田 俊彦 |
| 短歌鑑賞 ―前川佐美雄「あかあかと…」― | |
| 鎌倉の稲荷(中) | 三橋 健 |
| 城下町会津若松とその周辺における稲荷信仰 | 野沢 謙治 |
| 稲荷信仰に於ける「玉と鍵」を巡って | 稲垣 善彦 |
| 狐の嫁入りと狐火 | 阿基 米得 |
| 大都市とその近郊の稲荷祠 | 藤田 豊 |
| お稲荷さんめぐり ―ささやかな庶民の願いを伝える― |
西尾 忠久 |
| 女化(おなばけ)稲荷神社 | いのうえ 田堂 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。