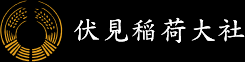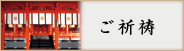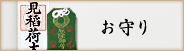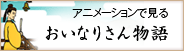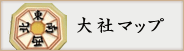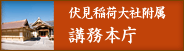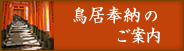当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」28号
| 稲荷明神講式と荷田講式 | 小島 鉦作 |
| 稲荷信仰の背景とその性格 | 渡邉 昭五 |
| 稲荷明神の利生譚 ―進命婦を中心として― | 近藤 喜博 |
| 「大祓の詞」考 ―日本語の系統問題から― | 芝 烝 |
| 稲荷信仰の習合構造 | 高橋 渉 |
| 稲荷大社十景 短歌 | 井ノ本 勇象 |
| 「好去好来」宮司対談 | 皆川 月華 坪原 喜三郎 |
| 狐信仰の民俗発想因子論 | 石上 堅 |
| 霜月祭と屋敷稲荷 | 佐々木 勝 |
| 稲荷信仰と道祖神信仰との接点 伊豆相模における習合例 | 木村 博 |
| 伏見北から南へ ―芝居散策― | 角田 豊正 |
| 舞台にあらわれる狐たち | 権藤 芳一 |
| お狐さんと長唄 | 鈴木 浩平 |
| 銀座の稲荷 | 島田 裕巳 石井 研士 |
| お田植祭・萬燈会 俳句 | 小森 洛中子 |
| 太郎稲荷繁昌志 | 宮尾 與男 |
| 稲荷信仰の浸透 | 宮田 登 |
| 稲荷信仰 | 宮本 袈裟雄 |
| 中世における稲荷神社とその祭礼課役 ―馬上役を中心として― | 宇津 純 |
| 強い丹波篠山藩の力士たちの正体は? 王地山負け嫌い稲荷の由来伝説 |
いのうえ 田堂 |
刊行物「朱」27号
| 倉稲魂神と納戸神 | 石塚 尊俊 |
| 命婦と狐 | 加納 重文 |
| 稲に対する信仰の原点へ | 池田 源太 |
| 発心集所収の桓舜稲荷参篭の話の周辺 | 高尾 稔 |
| お稲荷さんと芝居 | 角田 豊正 |
| 稲荷信仰と伏見人形 | 奥村 寛純 |
| でっちでんぼ連想記 ―わらべ唄― | 川田 ひさを |
| 朱色起源考 補遺 ―五行説と朱色― | 藤田 豊 |
| 「稲荷神」の習合問題 | 高橋 渉 |
| 春山見神 短歌 | 山本 牧彦 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 井上 太一 坪原 喜三郎 |
| 補訂「山城国風土記逸文について」 | 高藤 昇 |
| 幕末大和の稲荷踊り | 吉田 栄治郎 |
| 「稲荷」でない「稲荷」の話 ―「御船歌」を例に― |
木村 博 |
| 稲荷信仰私見 ―陰陽五行思想による 稲荷の再吟味― |
吉野 裕子 |
| 小田原城と狐と蛙石 ―北条稲荷縁起秘話― | いのうえ 田堂 |
| 稲荷史六つの謎 | 山上 伊豆母 |
| 稲荷社の起源 | 西田 長男 |
| 戦後における伏見稲荷大社研究の成果と課題 | 三橋 健 |
刊行物「朱」26号
| 狐女房と稲荷信仰 | 長野 一雄 |
| 稲荷町のこと | 権藤 芳一 |
| 鈴の音 短歌 | 山本 牧彦 |
| 狐ホカイの前後左右 | 石上 堅 |
| 初詣 俳句 | 桂 樟蹊子 |
| 狐と暮らしてきた日本人 | 戸井田 道三 |
| 稲荷大社元旦参詣の賦 短歌 | 平井 乙麿 |
| 稲荷山と門前町 ―私にとって稲荷信仰とは何か― |
神馬 彌三郎 |
| 狐のうそとまこと | 大岡 信 |
| 護法と護法とび | 土井 卓治 |
| 農村の稲荷信仰 ―埼玉県戸田市の事例― | 大島 建彦 |
| 折り折りの師 ―好去好来― | 守屋 光春 |
| 心が澄む…如月随想 | 中村 直勝 |
| 朱色起源考 ―お稲荷様の鳥居はなぜあかい― | 藤田 豊 |
| 荷田氏所伝の稲荷社縁起 | 西田 長男 |
| 伏見稲荷大社本願所の成立と消長 | 菊地 武 |
| 稲荷の神について | 肥後 和男 |
| 飛脚狐の宮・与次郎稲荷 | いのうえ 田堂 |
| 稲荷の神 随想 | 林 真作 |
| 長禄四年銘の鰐口を発見する | 木村 博 |
| 大阪商人と伏見稲荷 | 米谷 修 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。