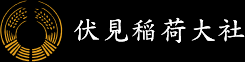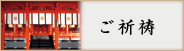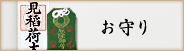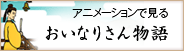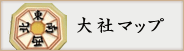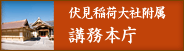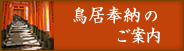当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」10号
| 近世和歌雑考 | 久松 潜一 |
| 天阿上人と稲荷神道 | 小島 鉦作 |
| お田植祭 短歌 | 前川 佐美雄 前川 緑 |
| 御田 俳句 | 山口 誓子 山口 波津子 |
| ウカノミタマ再考 | 肥後 和男 |
| 稲荷と平家物語 | 赤松 俊秀 |
| 金棯豊韻図 口絵 | 棟方 志功 |
| ここにも赤い鳥居が | 柴田 実 |
| 日本新頌 詩 | 樋口 大學 |
| お稲荷さんの思いで | 坂本 太郎 |
| 赤い鳥居 | 安田 青風 |
| 満州で迎えた終戦と稲荷明神 | 森 克己 |
| みのり | 国分 綾子 |
| 九郎助稲荷の講中 | 鴇田島 一二郎 |
| 科学技術と宗教 | 森 政弘 |
| 京都と稲荷社 ―御霊会としての稲荷祭― |
林屋 辰三郎 |
| 名乗りの源流 | 上田 正昭 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 滝川 政次郎 守屋 光春 |
| 稲の文化史 | 樋口 清之 |
| 田中の神と四の大神 | 出雲路 敬和 |
| 稲荷信仰序説(二) イナリ信仰覚書・7 | 近藤 喜博 |
| 「しるしの杉」の原像 | 山上 伊豆母 |
| 稲荷山吟行十三首 短歌 | 中河 与一ほか |
| 稲荷山の経塚 | 三宅 敏之 |
| 東丸の国学校創立の啓文 | 羽倉 敬尚 |
| 稲荷大社拝殿軒下の鉄造十二宮の吊り灯篭 | 田中 重久 |
| 稲荷のうた 詩 | 臼井 喜之介 |
| 古式の祭具を残した稲荷神社の冬祭 | 井上 頼寿 |
| 信仰と未信仰 | 森田 峠 |
| お稲荷さんと私 | 中村 扇雀 |
刊行物「朱」9号
| 京都市内の稲荷神社の氏子区域 | 岩橋 小弥太 |
| 初詣の稲荷山 俳句 | 虚子 選 |
| 稲荷の川柳 | 麻生 磯次 |
| 九郎助稲荷とその氏子 | 滝川 政次郎 |
| 火華旺韻図 口絵 | 棟方 志功 |
| 初午詣 俳句 | 増田 手古奈 |
| 雨の朱の宮 短歌 | 鴇田島 一二郎 |
| 氏神としての稲荷社 | 原田 敏明 |
| 稲荷山の秋 いなりにちなむ謡曲四題 | 岡本 吉二郎 |
| 落語のお稲荷さん | 宇井 無愁 |
| 稲荷の神と歌 | 安田 章生 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 山口 誓 守屋 光春 |
| 稲荷信仰序説(一)イナリ信仰覚書・6 | 近藤 喜博 |
| 初午献句 | 手古奈 選 |
| 水草の花 | 桑原 専渓 |
| 俳句に見る稲荷大社祭事(承前) | 高桑 義生 |
| 食物の主宰・生産産業守護の大神 | 植木 直一郎 |
| 荷田東丸の学統(下) | 羽倉 敬尚 |
| お稲荷さんと狐 | 臼井 喜之介 |
| 伏見詣 | 大内 青圃 |
| 初旅の伏見・桃山 | 渡辺 保 |
| 真言宗寺院に於ける稲荷信仰 | 味岡 良戒 |
| お稲荷さんの思い出 | 楳茂都 陸平 |
刊行物「朱」8号
| 年中行事絵巻伏見稲荷大社本 | 福山 敏男 |
| 宮廷と稲荷大社 | 奥野 高廣 |
| 藪かげの狐語り | 石上 堅 |
| 稲荷山即事 短歌 | 春日井 瀇 |
| 神います 俳句 | 桂 樟蹊子 |
| 稲荷社に於ける神仏分離に就いて | 久保 輝雄 |
| 摂津守信郷勧進稲荷十二景 和歌 | 小澤 芦庵 |
| 「好去好来」 宮司対談 | 前川 佐美雄 守屋 光春 |
| 日昇昴韻図 口絵 | 棟方 志功 |
| 文学の中の稲荷 | 若松 正一 |
| 古典にみられる稲荷信仰 | 鎌田 純一 |
| 草餅・蓬餅と粽と解餅 | 高木 蒼梧 |
| 俳句に見る初詣と初午 | 高桑 義生 |
| 西洞院家の写本「社格記」 | 井上 頼寿 |
| いなづま会選句抄 俳句 | 青畝ほか |
| 荷田東丸の学統(上) | 羽倉 敬尚 |
| お稲荷さんと私 | 鈴木 青々 |
| 御守護をいただいて四十年 | 高田 浩吉 |
| こんなおはなし | 桂 米紫 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。