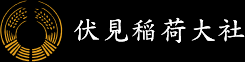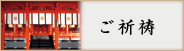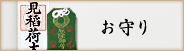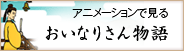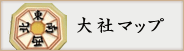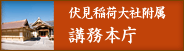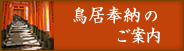当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」68号
| 稲荷信仰と和歌・連歌断章 | 伊 藤 伸 江 |
| 稲荷祭の神輿渡御ルート-院政期を中心として- | 中 村 太 一 |
| 宝剣小狐丸の威徳-〈小鍛冶〉〈紅葉狩〉から『雪女物語』へ- | 石 井 倫 子 |
| 「山城国紀伊郡里々坪付帳」にみえる稲荷社領について | 野 村 朋 弘 |
| 古代文学の韻文の「伏見」 | 小 田 剛 |
| 伏見宮貞成『看聞日記』にみえる伏見稲荷社 | 薗 部 寿 樹 |
| 「恋しくは」考――葛の葉伝説における和歌の力―― | 田 村 正 彦 |
| 王子稲荷の狐火伝承から「王子狐の行列」へ | 米 山 孝 子 |
| 変身する場所としての「うつぼ」-『道成寺縁起絵巻』とそれに先行する物語群- | 渡 邊 浩 史 |
| 狐に関する昔話、童話のことなど | 大 伏 春 美 |
| 鬼除け・厄除け樹木 ヒイラギ・トベラ・タラノキ・キササゲ考 | 渡 辺 弘 之 |
| 「赤い袈裟」の智慧~記号から象徴へ~ | 谷 青藍(麻理) |
| 牧野富太郎博士と鵜殿のよし-未来につなぐヨシ原- | 支 倉 千賀子 |
| 田 中 純 子 | |
| 池 田 博 | |
| 館林城の尾曳伝説-狐築城伝承の発生と展開- | 板 橋 春 夫 |
| 呑香稲荷神社神代神楽の歴史と現在 | 橋 本 裕 之 |
| 〈史料翻刻〉享保一六年 大西親盛日記(二) | 上 島 亮 平 |
刊行物「朱」67号
| 『永久百首』「稲荷詣」題の歌を読む | 家 永 香 織 |
| 院政期歌人の詠歌環境―『永久百首』「稲荷詣」題をめぐって― | 溝 端 悠 朗 |
| 『篁物語』における「食」―稲荷詣を端緒として― | 荻 田 みどり |
| 疫病をしずめた鎌倉の佐助稲荷神社 | 三 橋 健 |
| 厄除け・魔除けの植物 | 渡 辺 弘 之 |
| 伏見稲荷大社・稲荷山の水晶 |
貴 治 康 夫 三 上 禎 次 |
| 伏見稲荷大社・稲荷山周辺に生息するプラナリア | 西 谷 信一郎 |
| 古代文学の散文の「伏見」 | 小 田 剛 |
| 田の神と稲荷の翁―越前地方の神像に見る分類 | 金 田 久 璋 |
| 官幣大社稲荷神社宮司近藤芳介の山口時代―幕末長州藩関連資料から | 小 野 美 典 |
| 鳥取藩主池田慶徳の稲荷信仰~大名の庭に祀られる産土神~ | 伊 藤 康 晴 |
| 〈資料紹介〉アメリカ女性の見た日本――稲荷神社の石のキツネなど | 錦 仁 |
| 〈史料翻刻〉享保一六年 大西親盛日記(一) | 上 島 亮 平 |
刊行物「朱」66号
| 長講堂領伏見御領の形成過程 | 吉 江 崇 |
| 秦氏の開発伝承と祭祀 | 仁 藤 敦 史 |
| 平安京の都市民と稲荷祭 | 久 米 舞 子 |
| 京都の氏子区域の形成 ―稲荷社と松尾社― | 黒 田 一 充 |
| 石川淳と狐 ―現実の論理と物語の論理と | 山 口 俊 雄 |
| 伏見稲荷大社境内の樹木 | 渡 辺 弘 之 |
| 伏見稲荷の森のきのこ三十二選 | 森 本 繁 雄 |
| 江戸時代御会和歌と「冷泉為村卿歌集」 | 古 相 正 美 |
| 〈史料紹介〉伏見稲荷大社蔵「稲荷社月次御法楽和歌」(二) | 早乙女 牧 人 |
| 古代文学の韻文の「稲荷」 | 小 田 剛 |
| 「平安時代の狐」補遺 ―年表と「小狐」他再び― | 中 島 和歌子 |
| 比叡山における稲荷信仰 ―《日吉山王垂迹神曼荼羅》の作例から― | 坂 口 泰 章 |
| 狐の秘法と中世開発 ―水資源開発の宗教的対応に関する予察― | 渡 邊 浩 貴 |
| 色の名前 ~臙脂における一考察~ | 谷 麻 理 |
| 明治期の英文ガイドブックに紹介された伏見稲荷大社 | 千代間 泉 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。