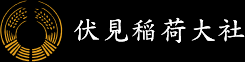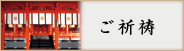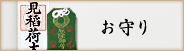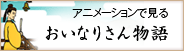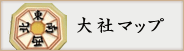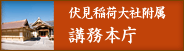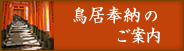当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」62号
| 立命館大学図書館蔵『後水尾院御集』について | 川 崎 佐知子 |
| 名所「伏見」「深草」と「稲荷」―宗祇の選択 | 赤 瀬 知 子 |
| 十五世紀の伏見稲荷社に関する雑考―『満済准后日記』『看聞日記』を中心に― | 呉 座 勇 一 |
| 小説の材料考―谷崎潤一郎『紀伊国狐憑漆掻語』 | 中 村 ともえ |
| 清少納言の祈り―『枕草子』における稲荷を始発として― | 春 日 美 穂 |
| 古代史上の狐信仰―動物が神使となるまで― | 中 村 一 晴 |
| 狐火伝承と俳諧 | 久留島 元 |
| 「憑き物」使いの一系譜―狐使いを中心にして― | 酒 向 伸 行 |
| 泉鏡花『菊あはせ』小考―「稲荷堂」と「狐」を手がかりに― | 西 尾 元 伸 |
| 稲荷山に祀られる神 | 武 部 智 子 |
| 山形市「歌懸稲荷社」の由来と最上義光の文事との関係について | 名 子 喜久雄 |
| お稲荷さんの想い出 | 松 井 今朝子 |
| 狂言「石神」の構想と演出―石神信仰との関連― | 稲 田 秀 雄 |
| 稲荷神社から金物神社へ―金物のまち三木における「鞴祭り」の変遷― | 岡 本 真 生 |
| 式子内親王の「伏見」の歌注釈 | 小 田 剛 |
| 稲荷信仰と大嘗祭 | 佐々木 聖 使 |
| 京師巡覧〈稲荷〉贅註 | 鈴 木 元 |
| 室町時代における稲荷祭礼東寺中門御供の変化について―東寺執行公人を中心に― | 酒 匂 由紀子 |
| 稲荷信仰にみた神璽の様相―近世の神体勧請を手掛かりに― | 吉 永 博 彰 |
| 伏見稲荷大社と本居宣長 | 編 集 部 |
刊行物「朱」61号
| 骨皮道賢の女装ー日本中世における女性観の転換 | 早島 大祐 |
| 中世の伏見稲荷をめぐる信仰と芸能 | 石黒 吉次郎 |
| 元亀四年の稲荷祭 -「御鬮」をとる- |
河内 将芳 |
| 妖しい火 -狐火と蛍火- | 山﨑 みどり |
| 「樹伐の罪」と「稲荷神の祟」について | 小林 宣彦 |
| 秦造河勝と常世の神の歌謡 |
藤原 享和 |
| 新史料 刀工宮本包則の稲荷山打ち脇差について | 塚田 志穂 |
| 大山為起と荷田春満 -『古事記』注釈の比較・続考 |
齋藤 公太 |
| 赤と人間 | 坂田 勝亮 |
| 岡本かの子と〈狐〉 -岡本かの子「狐」小考- |
野田 直恵 |
| 淳和天皇朝の稲荷神社 | 久禮 旦雄 |
| 「稲荷」題の歌の表現について | 近藤 美奈子 |
| 細見美術館「竹生島弁財天像」 小解 -応永の施入銘をもつ騎狐の女神画像をめぐって- | 杉﨑 貴英 |
| 初期六字経法の形とその変容-「三類形」(天狐・地狐・人形)の作法から考える- | 小田 悦代 |
| 歌舞伎『芦屋道満大内鑑』における「狐」の表象 | 雨宮 久美 |
| 漁業信仰と稲荷信仰 -三重県南部の事例から- | 髙木 大祐 |
|
伏見稲荷大社と応仁の乱 |
編集部 |
|
|
刊行物「朱」60号
| 有栖川宮の雅印を刻した篆刻家・羽倉可亭 ―「春夜宴桃李園序」原添聯幅と書入本『熾仁親王印譜』から浮かび上がる新事実を中心に― | 内田 誠一 |
| 白川資雅と「狐」 | 田村 航 |
| 中国語訳『源氏物語』小考 ―狐描写の訳出状況を探る― |
笹生 美貴子 |
| 近江栗太郡手原稲荷神社の成立過程 |
高田 照世 |
| 出雲への神集い伝承と稲荷神 | 品川 知彦 |
| 『秀真政伝紀』にみる稲荷の狐について |
吉田 唯 |
| 平安朝における歌枕としての稲荷(山) | 小田 剛 |
| 橘と秦氏と能 狐と伏見稲荷大社とのつながりなど |
吉武 利文 |
| 『伊勢物語』を統一体と見て一二三段を中心につなぎ読む ―成立論的読みでなく相補論的読みを適用することの妥当性― | 田口 尚幸 |
| 御膳谷奉拝所・御饌石と井上頼寿 ―「御旅所考」にふれながら― |
大東 敬明 |
| 女の目、男の目 ―稲荷の女をめぐる赤染衛門と大江匡衡 |
荒木 浩 |
| 『玉水物語』構想論 | 真下 美弥子 |
| 鶉となりて ―深草考― |
内田 美由紀 |
| 宝登山(埼玉県秩父郡長瀞町)の宝玉稲荷神社について | 西村 敏也 |
|
|
|
|
|
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。