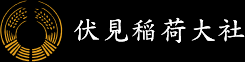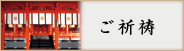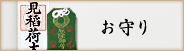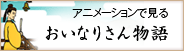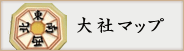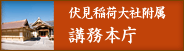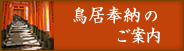当社では昭和42年より機関誌「朱」を発行いたしております。
内容は「稲荷」に関する論文・随想などとなっております。
刊行物「朱」50号
| 『山城国風土記』と稲荷社 | 荊木 美行 |
| 稲荷大社の縁起と神仏習合 | 寺川 眞知夫 |
| 東海道本線稲荷駅 | 木津 勝 |
| 小倉の狐物語 ―『小笠原流礼忠孝』の周辺― |
安冨 順 |
| 菅楯彦、奥谷秋石、阪正臣、山本行範による合作「きつねのよめいりの巻」 | 中谷 伸生 |
| 稲荷使藤原隆宗 | 槙野 廣造 |
| ヨーロッパの霊狐 | 高尾 謙史 |
| 稲城について | 松尾 光 |
| 蘆庵門の稲荷祠官の和歌短冊 | 大取 一馬 |
| 歴史時代の災害と稲荷祭 | 片平 博文 |
| 相槌の稲荷開帳と狐芸の流行 ―明和元年の青蓮院・光則寺の出開帳をめぐって― |
末松 憲子 |
| 近世前期における稲荷社家と吉田家 ―神道伝授と元禄七年社殿修造一件― |
幡鎌 一弘 |
| 狐魅譚変容―近代文学における〈狐〉― | 千葉 俊二 |
| 稲・銭と富の観念 | 三上 喜孝 |
| 熊谷稲荷の唱導と文芸 | 堤 邦彦 |
| 朱砂と水銀 | 市毛 勲 |
| 大永八年の稲荷・東福寺喧嘩について ―『稙通公記』を中心に― |
河内 将芳 |
刊行物「朱」49号
| 社毀(やしろこぼ)れて神さびし時の実在性 ー梁塵秘抄の稲荷信仰(その一)- |
渡邊 昭五 |
| 商業神としての稲荷信仰の成立と展開 ー向島小梅村三囲稲荷を事例としてー |
若杉 温 |
| 文学にみる狐にかかわる色 | 伊原 昭 |
| 阿波足利氏の守札 | 長谷川 賢二 |
| 日本人の忘れものとお稲荷さんの「葱」 | 久保 功 |
| 「本槐門・新槐門図序文」について ー九条殿・宇賀塚・深草祭をめぐる説話と歴史ー |
藤原 重雄 |
| 稲荷御読経僧尋光 | 槙野 廣造 |
| めりやす「信田妻」の復曲 | 配川 美加 |
| 朱とベンガラー顕微鏡で見る考古資料ー | 本田 光子 |
| 高岡城と稲荷大明神 ー聚楽第型城郭に祀られる意義ー |
高尾 哲史 |
| 芝居と稲荷大明神 | 大橋 正叔 |
| 中世イギリスの狐 | 池上 惠子 |
| 秦氏由来の遺跡踏査記(八) | 段 煕麟 |
| 稲荷と桃太郎ー初午・お伽・桃太郎祭ー | 齊藤 純 |
| 伏見稲荷大社と鳥居 | 宮本 三郎 |
| 『万葉集』における「朱」 -詩歌表現の和製ー |
井上 さやか |
| 近世大坂の稲荷社祠 | 井上 智勝 |
刊行物「朱」48号
| 女夫狐 | 古井戸 秀夫 |
| 空海・弘法大師と稲荷信仰 | 頼富 本宏 |
| 伏見中納言師仲と平治の乱 | 元木 泰雄 |
| 稲荷社祠官著作の由緒記と荷田春満の神代巻解釈 | 松本 久史 |
| 伏見稲荷大社の能舞台の造形 | 横山 勉 |
| 狐の怪異と源氏物語 | 上野 辰義 |
| ナニワイバラ稲荷山に自生 | 村田 源 |
| 「心のまつ」と「杉むら」と ー赤染衛門の和歌の詠作事情をめぐってー |
西 耕生 |
| 稲荷社と柳営連歌 | 入口 敦志 |
| 想狐連環記ー母性の鑑としての「狐」から発してー | 千 草子 |
| 永久元年十一月二十六日 鳥羽天皇の稲荷行幸 付、藤原為房のこと |
槙野 廣造 |
| 稲荷信仰の展開と修験ー護符を中心にー | 宮家 準 |
| 深草周辺の地名お扱った江戸の草双紙について | 丹 和浩 |
| 近世畿内における飛礫について | 村上 紀夫 |
| 狐の施行と稲荷行者 | 赤田 光男 |
| 『雑談集』地名としての「稲荷」 ー説話の話型と固有名詞をめぐってー |
廣田 収 |
| 傳、伏見稲荷山出土の方格規矩獣文鏡二面 | 近江 昌司 |
| 大阪城と狐 | 北川 央 |
| 〈しるしの杉〉と『蜻蛉日記』 | 吉田 幹生 |
| 島津家と稲荷大明神・狐 | 安藤 保 |
当誌は非売品ですがご希望があればお頒ちいたします。
但し残数に限りがありますので「宣揚部」までお問い合わせください。